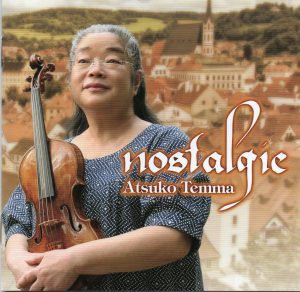- Home
- 「小津安二郎 人と仕事」より
- 看護日誌 ―おやじ小津安二郎はもういない―
看護日誌 ―おやじ小津安二郎はもういない―
小津安二郎の最期を看取ったのは、俳優佐田啓二でした。小津監督と佐田啓二は、実の親子のように親密な間柄だったのです。佐田夫人の益子さんは、松竹大船撮影所近くにあった月ヶ瀬食堂の看板娘で、小津監督は益子さんが大のお気に入りでした。益子さんを娘のように可愛がった小津監督は、私設秘書としてあちこちに連れ回していたとのことです。
しかし、親子ほど年が離れているとはいえ、独身の小津監督にとって、益子さんは単なる娘としての存在ではなかったのでしょう。その後、佐田啓二と益子さんは結婚することになり、佐田が自ら小津監督へ報告する際には大変に緊張したそうです。この逸話を聞いて、私は「彼岸花」で佐田啓二が佐分利信の会社へ、初めて訪ねるシーンを思い浮かべました。
佐田啓二と娘役の有馬稲子の結婚を、内心快く思わない父佐分利信の役は、実は佐田から益子さんとの結婚を聞かされた小津自身の姿ではなかったでしょうか。ぶっきらぼうに「お父さんは、そんな結婚は断固として認めないからね。」と言い放つ佐分利信の姿こそ、佐田啓二と益子さんに対する小津監督の本音ではないか、と私には思えてなりません。
また、「秋刀魚の味」では、北龍二が娘のように若い妻と再婚し、笠智衆と中村伸郎に「若い嫁はいいもんだぞ。」とのろけるシーンがあります。それに対して、中村伸郎は「ああ、いやだいやだ、ああはなりたくないね。」と負け惜しみを言います。笠智衆は北龍二に「あれ、飲んでるのか?」と聞き、精力剤を飲む仕草をしますが、北龍二は嬉しそうに「必要ないんだ。」と答えます。
この一連のやり取りの中にも、本当は若い娘と結婚したかったという、小津監督の益子さんとの結婚願望が隠されているように感じます。そして、ラストの方では、娘を嫁に送り出したあと一人で酒を呑み、娘がいなくなった台所で涙ぐみ、「ひとりぼっちか。」とつぶやく笠智衆の姿を映し出しますが、晩年の小津監督自身の姿とオーバーラップするようです。
実際に、小津監督は佐田啓二と益子さんの結婚式のあと、深酒をして酔いつぶれたそうです。そんな小津監督と佐田啓二夫妻との関係は、その後は本当の親子のように親密になっていったのです。
1964年(昭和39年)8月17日、佐田啓二は4日前から益子さんと小津監督ゆかりの地である蓼科高原の別荘へ避暑に訪れていましたが、NHKドラマ『虹の設計』収録のために自動車で帰京する途中、韮崎市韮崎町の塩川橋欄干に激突し、勢い余って別の乗用車へも衝突する大事故を起こしました。
小津監督の死からわずか8ヵ月後、まだ37歳のあまりに早すぎる死でした。益子夫人は、寂しがり屋の小津監督が佐田啓二をあの世へ連れて行ってしまったと言って嘆いたそうです。
「看護日誌」には、死期のせまった小津安二郎の様子が克明に記録されています。以下にサンデー毎日(昭和38年12月29日号)より、佐田啓二の「看護日誌 ―おやじ小津安二郎はもういない―」を引用してご紹介します。

中井麻素子(益子) 中井貴一 病床の小津
看護日誌 ―おやじ小津安二郎はもういない―
(サンデー毎日、昭和38年12月29日号より) 佐田啓二
3月26日
長野県蓼科の山荘にこもっているおやじさん(小津先生)から長距離電話がかかってきた。「どうしたんです?」「クビの横っちょにハレモノができてね、痛いんだよ」「ハレもの?」「医者にみてもらおうかな、ともかく帰りたいんだ。明日帰るからね。だけど知らない医者はイヤだよ。緒方先生(安雄博士)がいいな。そうだ、先生でなくちゃいやだ」電話はきれた。緒方先生は、私の家の近所にお住まいで、先年長男貴一の初節句パーティにご招待し、その席でおやじさんと初対面された。お二人は非常に意気投合した様子で、おやじさんの映画「秋刀魚の味」の同窓会シーンに特別出演されたこともある。しかし緒方先生は小児科が専門だ。老童とはいえ大きな大人のおやじさんのハレモノは専門外ではないか。3月31日
十二時大船駅でおやじさんと待ち合わせ、緒方先生を山王病院におたずねした。「どういうぐあいですか」「とても痛くて熱が少しあるような気がします」「私は子供の病気ならわかるんですが、大人の病気はわかりません。友人の前田外科をご紹介しましょう。手術をするにしても三十分ぐらいですむと思いますから」緒方先生につきそわれて、前田外科に行った。所用があって私は二時間ほど中座し、また前田外科にもどった。そのとき、緒方先生と前田院長が何かヒソヒソ話をしていた。私の顔をみると前田院長は「これは、すぐ手術したほうがいいです」といわれた。さて、どこで手術するか。緒方先生は、築地の国立がんセンターの久留院長に頼みましょうといわれた。久留先生は、偶然、おやじさんの松阪中学時代の同窓生ということであった。おやじは人見知りをする。知らない人に、からだをまかせるのはイヤだ、イヤだと、しきりに言う。4月10日
がんセンターに入院した。新橋演舞場の建物が鼻さきに見える四階の病室。まっ白い壁にとりかこまれたベッドに、寝間着を着てちょこんとすわったおやじさんは、心もとなさそうな顔をしていた。
でも、しかたがない。ハレモノを退治するまでは……。4月17日
手術日。
簡単にすむというので、手術室の前で待っていた。痛いのが何よりきらいで、注射を子供のようにこわがっていたおやじさんが、こともあろうに首にメスを入れられている。ひどく長びいているようだ。少々心配になる。しかしこれまで病気したことがないおやじさんだ。痛い思いもしたことがない。普通の人よりそれだけ恵まれてきたのだから今度くらい……しかたあるまい。
手術室のドアがあいて、看護婦さんがとび出してきた。「アバれてクルマから落っこちそうになるんです。力の強い人、おさえにきてください」とんで行くと、おやじさんは痛がって「ナンマイダ、ナンマイダ」といっている。「念仏なんて縁起でもない」と言うと、「痛くて痛くて、何か言ってないとたまらないんだ。言わせてくれよ、ナンマイダ」悶えながらなお続けた。
七月一日まで八十二日間、おやじさんは、がんセンターにいた。
手術のあと、精密検査を受け、首にできていた小さな潰瘍を除いてもらい、手術のあとに、コバルト、ラジウム療法を施した。それは〝ガン〟の治療法である、と私はきいていた。一週間ずつ患部にコバルトとラジウムの針をさすのである。クギのような針を十本もさすので、首はぜんぜん動かせない。石地蔵みたいになっていた。
「六十年生きてきて、いちども長かったと思ったことはなかったが、針を入れられた一週間の長さときたら、どう説明していいかわからないよ」。針を抜いたあと、おやじさんは見違えるほどげっそりやつれて何度も〝説明できないよ〟とくりかえした。「そのへんにオノか何かあったら自殺したかったよ。この病院は設備が悪いから、そういう便利なものがないんだ。お医者というのは〝痛み〟を治療することはしないんだね。〝痛いですか〟〝痛いですよ〟〝そうですか〟ってんだからね。病気をなおすことはしても〝痛み〟はダメなんだね」〝痛み〟の悪口を、おやじさんは言い続けた。
「それにしても、先生、ガンだったのかもしれませんね、ガンマーやラジウムやられたんだから」というと、「そうだね、これでオレも一人前のトウフ屋になれたよ、ガンモドキつくったんだからな」と大笑いした。
次回作は「大根と人参」――親友野田高梧氏と、シナリオ執筆のため、正月から蓼科にこもった。「こんどはどんな話にしようか」「そうだねえ、こんなのはどうだい、ガンがはやってるだろう。ガンでよく人が死ぬだろう。オヤジか何かがガンにかかってさ、それを知らそうか、知らすまいかと、ゴタゴタ、ワイワイするのはどうだい」「いいだろう。イケるね。それにしよう」。
いつものように、食べものから日用品に至るまで、鎌倉から運ぶので西部劇の大移動のようだった。
「大根と人参」では、そのガンになる人まで配役が決っていた。「原稿にとりかかろうか……と思っていたら、ハレモノができたんだ」野田先生は残念そうにいわれた。
私たちは小津先生の人間的影響を受けてか、なにごとにも、のんびりした反応しか示さない。あんな〝グミ〟みたいなハレモノが〝ガン〟のしらせなどとは思いもよらなかった。それで二人で、ガンモドキがつくれたなどと他愛もなく笑っていたのだ。
見舞客はあとを断たなかった。一日四、五十人も見えた。病院側がおどろいて、一人五分以内に制限した方がいいと忠告に来た。「随分入りがいいじゃないですか」「ウン、題名がよかったよ、がんセンターだからな」「こんなに入りがよくちゃ、ロングランしなきゃいけませんね」「ウン、ちょいと退院するわけにいかないね」。
毎週金曜日、私の長女の貴恵子が、おやじさんを見舞った。私には特にいわなかったが、おやじさんはそれを楽しみにしていたらしい。貴恵子のために、おやじさんはクレヨンと画用紙を買っておいてくれた。二人でいっしょに絵を描くのである。毎週一枚仕上げる約束だった。花や、私の顔や、妻の顔や、また見舞いに来合わせたスタッフの顔を、貴恵子はおやじさんと喋りながら描いた。でき上ると白い壁にはりつけた。それが二十枚にもなったろうか。七月一日の退院の日に、おやじさんは自分でその絵を一枚々々はずした。
「どうするんですか」と聞くと「持って帰るんだ。貴恵子ちゃんがはたちになるまでとっておいて、昔、こんな絵を描いたんだよ、と出して見せてやるんだ」といわれた。
鎌倉に帰る間じゅう、車の中でおやじさんははしゃいだ。丈夫だった時のいつものスタイル、白いピケ帽にまっ白なワイシャツ、それに仕立ておろしのズボン。首に白い包帯のあるのが、丈夫な時と違っているだけだった。
退院する数日前に、こんなことがあった。
「オレ、洋服新調するよ」と言い出した。「いま、痩せてるのに作ったら、ふとった時着られませんよ」と言うと、「いやね、Iという男がいてね、ふとってたんだよ。それが病気してね、なおって出てきたんだが、服がダブダブなんだ。みっともなかったよ。そんなとき昔の洋服着るのはよくないよ。だから新調するんだ」と言い張る。生地を持ってこさせて二着つくることにした。所が翌日「やめたよ」と言う。「どうしたんですか」「いま夏だろう、ワイシャツでいいよ。それに秋になったら、またどんなスタイルがはやるかもわからないしね、やめたよ」。スタイリストのおやじさん。ダブダブの服はイヤだよ、からファッションの心配までしている。私は、うちにあった生地でズボンだけ新調して上げることにした。
鎌倉の家に帰って、まず祝杯、糖尿のケがあるので日本酒ブドー酒は禁じられ、ウィスキーかブランデーだけ許されていた。ナポレオンをとり出して、おやじさんは、グラス(いつものタマゴ立てのグラス)で三杯ものんだろうか、今までなら絶対に赤くならなかったのに、その夜はゆでエビのように赤くなった。私の妻が言った、「先生、そんな純情な先生みたことないわ」。そのあと、うなぎを食べ、おやじさんは八十日ぶりに鎌倉の生活にもどった。
一週間ほどは快適な生活が続いた。右手が少ししびれるぐらいだった。しかし強くさすると痛がった。
湯河原温泉に湯治に行ったが一日一日しびれがひどくなり、完全な痛みに変っていった。七月末、鎌倉に帰り、電気をかけてみたりしたが一向に痛みは去らない。
八月は寝たきりの生活だった。私は一人で出かけて行って、食べられないというおやじさんの気を引きたて引きたて、いっしょに食事するようにした。「体力がつきませんよ」「食べられるような痛みじゃないんだ」「いけませんよ、食べなくちゃ」。押し問答をした。好物のさしみ、生うにの類も、痛みを押しもどさなかった。
おやじさんは、みんなといっしょにゴハンを食べ、酒をのむのが好きだった。松阪の育ちだから〝すきやき〟が好きで、またつくるのが上手だった。だいたい台所仕事が女性よりうまくて〝すきやき〟を煮るのも、肉は肉、野菜は野菜、きちんとならべて、手ぎわよく煮た。ハシさばきが見事であった。食道楽でもあった。珍味を沢山ならべて目じりを下げていた。そのおやじさんが、食べる楽しみを放棄しはじめた。
吸いのみにナポレオンを一滴落としてのんだのは、九月の何日だったろうか。それが最後のブランデーの味だった筈だ。一滴落とすと、吸いのみの水が、うすく色づいた。くちびるに一滴落とすと、おやじさんの顔が忽ち赤くなった。そして痛みがやや増したと訴えた。9月5日
がんセンターから、おやじさんは〝ガン〟におかされていると聞かされた。
〝ガン〟。〝ガン〟だ。
親しい者が集って相談した。”ガン〟であっても何とか再起させるのだ。
手術した四月十七日、久留院長が身内の人を呼ばれた。私にも来てほしいと、おやじさんの弟さんは言ったが、私は親しいが身内の人間ではない。遠慮して、久留先生のもとに伺わなかった。やがて弟さんか帰ってきて「どうでした?」と私が聞くと、「え? ええ。大丈夫だって言ってました。なおりますって‥…」。弟さんはそう言ったが、何かその言い方に不自然なものが感じられた。あの時からわかっていたのかもしれない――。
およそ疑惑すら持たなかった私たちだったが――。〝ガン〟ならば、何とか入院させなければいけない。9月6日
見舞いに行く。玄関の近くまで行くと呻き声が聞えた。苦しそうな声。
入院させなければいけない。しかし切り出せなかった。がんセンターはどうしてもイヤだと言い張る。9月15日
長男貴一といっしょに写真をとったことがない、という口実を設けて、おやじさんの写真をとった。
イヤだったろう、なんで写真なんかとるのだろう……と、おやじさんは思ったに違いない。それでも床に起き上がって私のカメラにおさまった。
白いヒゲがのびて痛々しい。心を鬼にしてシャッターを切った。
それでもなお入院について言い出せない。一刻をも争っているのに、どうしたことか。9月20日
「痛みには指数がないね。きょうは一一二とか一〇〇とかあらわせないんだ。痛いというコトバしかない。イタイ以外に言いあらわせないんだね」。もどかしそうに言った。
痛いので呻く。見舞いに来た客はびっくりして戸口まで来て帰ってしまう。しかし呻きながら人の気配を察していて「唸ってりゃ楽なんだから、上って行ってくれればいいのに」と気をつかった。9月30日
もう放っておくことはできない。鎌倉でのかかりつけの医者、足立先生と相談して今日、入院のことを言ってみようと決心した。妻は〝私のロからはどうしても言えない〟と台所の方へさがってしまった。私と二人きりになった。「痛くてゴハンが食べられない、これ以上の不幸はありません。痛み止めの注射(麻薬)以外に何かあるでしょう。がんセンター以外の病院には違った治療法があるでしょう。いっぺんそれを受けてみたらどうですか。ファイトを出して努力しなければいけません。痛い痛いと弱気になっていちゃ、なおりませんよ」。語気を強めてそう言った。おやじさんは意外と素直に、「たしかにそうだねえ。このまま死を待つことはないよ」と言った。
初めて〝死〟と言った。感づいているのだろうか。10月12日
東京医科歯科大学付属病院に再入院。松阪出身の稲葉助教授が引き受けてくれた。
ガンは相当に進んでおり、頸部の軟骨をおかしていた。十の治療法があるうち、もはや七つの方法はあてはまらないほどの進み方であると、先生は言われた。
こんな場所にガンが発生するのは、ガンの中でも悪質であると言われた。軟骨がやられているから、うっかり首を動かすと折れる心配がある、首にギプスをはめようとも言われた。何ということだろう。
入院は夜にした。おやじさんは床に坐ってじいっとしている。
「出かけますか」。声をかけると横を向いたまま「タバコ一本つけてくれ」と言われた。
喫い終ると、「ア、もういいよ」
「急ぐことないですよ」
「ウン。玄関から出してもらうか」
担架の上から「この道を酔っぱらってよく登って来たもんだ。今は下りだけれど、酔ってた時の方が苦しくなかったよ」
私は、おやじは二度と再び、生きてこの道をもどることはあるまい、と思った。小さなトンネルが途中にある。このトンネルも、今日が最後だろう。私たちは出来るだけゆっくりと担架をかついで行った。10月19日
「何も悪いコトをした覚えはないのに、どうしてこんな業病にかかったんだろうな」。天井を向いたまま、おやじさんが言った。「オレも、寝てるのは好きなんだがね。右足がどこにいっちゃったのかね、ベッドの下におっこちてるんじゃないかな。つらいもんだよ。痛いよ。ユメを見るんだ、このごろ。痛いユメばかりだよ」
「痛いユメって、どんな?」
「ワケのわからないコットウ品みたいな、さわったら痛そうなものばかり出て来るんだ」10月20日
オーデコロンを買ってくれという。このごろ床で用便するので、気になって仕方がない。布団の中にまきたいんだ、という。
シャネル五番のオーデコロンを買う。
三井弘次さんが見舞いに来た時、便をもよおした。「はずしましょうか」と聞くとはっきりしない。そのうち大きな呻き声をあげた。
びっくりした。「どうしたんです、先生?」のぞき込むと、「ナニ、いまウンがプップッいったからカムフラージュしたんだ。擬音を入れたんだよ」
六十になって便を附きそいの人にとってもらうハメになって、おやじさんはしみじみ言った。「おヨメさん、貰っとけばよかったよ。恥かしくていけないよ」11月7日
岡田茉莉子さんと吉田喜重監督が婚約の報告に見える。「なおったら一本とろうね、茉莉ちゃん」とおやじさん。
見舞い客がくると必ず「なおったら」と言う。11月14日
貴恵子の七五三、おやじさんに選んでもらった着物を着せて連れて行く。ちょうど眠っておられた。帰ろうかと思ったが寝顔を貴恵子に見せておこうと病室に入る。と、目をあけて、「おお、なんだ、貴恵子ちゃんか」
椅子の上に貴恵子をのせて対面させた。おやじさんと貴恵子は歌をうたった。「スーダラ節」と「幸福を売る男」の二つ。「スーダラ節」はおやじの好きな歌で貴恵子と二人でよく唱い、踊ったものだ。「幸福を売る男」は宝塚歌劇の女優さんたちと親しくなって覚え、好きになった。昨年二月、お母さんを亡くされた時も、この歌を追悼にうたった。
貴恵子はおやじさんと握手してサヨナラと言った。11月22日
白血球が少なくなり呼吸困難におちいる。稲葉先生は気管支の切開を提案された。ゴム管をつけて呼吸を補助するわけだ。
家族の方は反対。これ以上痛い目にあわせたくないという。しかし呼吸困難は痛いよりもっと苦しいのだからと手術を決行する。
手術後は言語障害が予想されたが、いたしかたない。11月27日
危険状態に入る。二、三度呼吸がとまった。弟さんが「ニイサン、ニイさん」と呼ぶと「うるさいよ」と小さく言った。11月28日
くちびるを動かしても、ことばが声にならない。イロハを紙に書き、壁にはった。おやじさんの口が動くと、私はイロハを順にさす。ミルクならミの字をさしたとき、おやじさんがコックリする。ミルクをのませる。11月30日
気力が衰え出す。12月2日
この十二日は、おやじさんの誕生日、還暦を迎える。妻は、お祝いにウールの羽織をあつらえた。特別に織らせたチャコール・グレーの無地に、朱色の布でおやじさんの家紋〝けんかたばみ〟をアップリケしたもの。
それを見て「いいね」。かすかに言った。
「十二日にさし上げますからね、それまでおあずかりしますよ」。
妻は羽織をたたんだ。12月11日
午前八時ごろ、容態が悪化した。駆けつけてみると死相があらわれていた。野田高梧氏ご夫妻はひと目みて「覚えていたくない顔だ」と目をつぶられた。
稲葉先生は私をよんで、「呼吸のしかたがよくありません。夜半か明け方が危険です。どこかへ出られるにしても三十分以内で来られるところにいてくださいよ」と言われた。私は十二日早朝から「モンローのような女」のセットがある。おやじさんの死に目には会えないのではないか。12月12日
………午後八時、柩に入って、おやじさんは鎌倉に帰ってきた。
もみじが散り敷く山道を柩をかついでくると、純白のかけ布の上に、おやじさんの好きだった赤い色をしたもみじが、二ひら、三ひら、散りかかった。