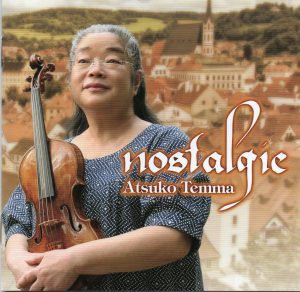「レコード芸術 2007年2月号」の記事より
片山杜秀氏は、政治思想史が専門の政治学者であり、慶應義塾大学法学部教授を務める傍ら、音楽評論家としても超一流の才人です。クラシック全般から映画音楽に至る幅広い見識の持ち主であり、気鋭の論客としてその才能を遺憾なく発揮されています。政治評論、音楽評論の両面において大変意義深い発言を行っており、最近メディア等でお見掛けする機会も増えてきています。
戦後の日本映画音楽にも大変造詣が深く、小津映画音楽のことで拙宅に訪れたことがあり、父にインタビューを行い記事を執筆しています。ずいぶん後になってから、当時の記事を拝読させていただきましたが、対話の様子から父と同世代か又はそれ以上のご高齢の方だとばかり思っていました。実際にはずっとお若い(私よりも年下)ことが分かり、その博識ぶりには本当に驚かされました。
「レコード芸術 2007年2月号」より、片山氏の執筆による「斎藤高順と小津安二郎」の記事を、以下に引用し掲載します。
斎藤高順と小津安二郎 片山杜秀
軍楽隊と弦楽器
大正一二年(一九二三年)の六月一日だから、関東大震災の丁度三ヶ月前である。東京の帝国ホテルで海軍軍楽隊が、各界の名士を招いて特別演奏会を催した。曲目はボロディンの《中央アジアの草原にて》やドヴォルザークの交響曲第九番《新世界より》。指揮は軍楽隊長の田中豊明だった。その年は、山田耕筰と近衛秀麿がNHK交響楽団の大もとになる日本交響楽協会を作る三年前になる。そんな頃合いに軍楽隊が《新世界より》をやっていた。もちろん全曲だ。
しかし、編成は? 軍楽隊だから吹奏楽編曲版? そうではなかった。通常の交響管弦楽だった。日露戦争の勝利の後、軍楽隊は陸軍も海軍も、大国の軍楽隊に相応しくグレードを上げなくてはと、管弦楽に手をのばした。隊員は、管打楽器だけでなく、弦楽器も兼任で練習した。そして、陸海軍とも、しばしば大曲を取り上げた。田中楽長時代の海軍軍楽隊なら《運命》も《英雄》も《悲愴》も弾いている。日本の交響楽史は、軍楽隊の活動を抜きには語れない。
すると、軍楽隊の弦楽教育はどう行われたのか。上野の東京音楽学校(現東京芸術大学音楽学部)の教官連が面倒をみたのである。たとえば、大正期の海軍軍楽隊にチェロを教えたのは、昭和に《海ゆかば》を作曲する信時潔である。信時は、上野の学生時代、チェロ専攻だった。
教えて貰うからには恩返しもせねばならない。たとえば昭和九年(一九三四年)十月末日、東京音楽学校のオーケストラは、R・シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》と《アルプス交響曲》という壮絶な曲目で、コンサートを開いた。指揮は、マーラーの弟子で同校教授のクラウス・プリングスハイム。コンサート・マスターはポラックで、ヴィオラのトップを《花嫁人形》の作曲家の杉山長谷夫が務め、その後ろには平井康三郎も居る。チェロには、唱歌《故郷》の作曲家、岡野貞一に、呉泰次郎、安部幸明、倉田高ら。チェレスタは山田一雄だ。同校の教官、卒業生、学生を結集した、今から見ると歴史展覧会のような顔ぶれである。では、管楽器は? 当時の上野では、それはあまり教えられていなかった。木管のかなり、金管の殆ど全員、それから打楽器もコントラバスも、海軍軍楽隊だった。上野側からは、ファゴットに片山穎太郎や金子登が居たりする程度。この日は、四十人近くもの軍楽隊員が賛助出演している。この時代、プリングスハイムは、師匠のマーラーの交響曲の連続演奏などもしているが、それもみな、軍楽隊の応援があってこそだった。
このように、大正から昭和にかけ、東京音楽学校と陸海軍軍楽隊はすこぶる密接だった。その関係から、軍楽隊が上野の生徒の駆け込み寺になったこともあった。昭和一八年、学徒出陣が始まると、音楽学生も例外では居られなかった。そこで、前途有望な者を、徴兵される前に軍楽隊に志願させる手口が編み出された。軍楽隊なら、普通の兵隊よりは戦死率も低いし、勉強にもなる。杉山長谷夫らが音楽学校を代表して交渉に当たり、昭和一九年、十三名の生徒が陸軍軍楽隊に引き取られた。彼らは普通の隊員として、管打楽器を学び、そこで敗戦を迎えた。
その中には、学校で下総皖一についていた團伊玖磨が居た。彼は戦後、今上天皇御成婚に捧げられた《祝典行進曲》など、数々の吹奏楽曲で名声を博した。オーケストラ作品では、ホルンを重用した肉厚な楽器法を売りにした。そういう基礎は、軍楽隊で培われたと考えてよい。
また、橋本國彦に習っていた芥川也寸志も居た。その出世作の《交響三章》や《交響管弦楽のための音楽》は、活発で技巧的でよく映える、木管や金管の用法によって際立つ。軍楽隊時代がなくては、こうは書けなかっただろう。
そして、斎藤高順が居た。信時潔に学んでいた彼は、仲間たちのうちでもいちばん軍楽隊経験を活かした音楽家になった。何しろ斎藤は、行進曲《輝く銀嶺》(昭和四三年)の成功で吹奏楽界に地位を固めると、その二年後には、航空自衛隊を象徴する音楽と言えばこれしかない、浮力も推力も十分な行進曲《ブルー・インパルス》を発表し、その功績もあって、昭和四七年に航空自衛隊航空音楽隊の隊長に就任するのである。隊長とはつまり首席指揮者だ。斎藤は上野では、プリングスハイムの弟子、金子登に指揮法を仕込まれていた。それが生きたのである。ついで、昭和五一年には、旧陸軍軍楽隊と歴史的につながりの深い警視庁音楽隊の隊長に招かれ、その地位に昭和六一年までとどまる。斎藤こそは、上野と軍楽隊の連携が生み出した最後の栄えある音楽家だったと言ってもよいだろう。無声映画館とポルカ
斎藤は、戦後、東京音楽学校に復学すると、新教官の池内友次郎や伊福部昭に師事して、昭和二四年に研究科を修了した。それから吹奏楽界で名声を得るまでは二十年近くある。その間、何をしていたのか。主には映画や放送の音楽を書いていた。映画では、巨匠、小津安二郎とコンビを組み、『東京物語』『早春』『東京暮色』、『彼岸花』『浮草』『秋日和』『秋刀魚の味』と、七本に作曲している。
この七本は、映画音楽の歴史を考えるとき、とても重い。小津と斎藤のコンビは、フェリーニとロータや、ゴジラと伊福部や、トリュフォーとドルリューにも匹敵すると、私は思う。
といっても、斎藤の音楽それ自体が個性的でユニークなのではない。むしろ、平凡で類型的である。といっても、それはわざとだ。斎藤は、小津が映画音楽に対して抱いていた欲求をひたすら忠実に具体化した。そうしたら、そういう音楽になる他なかったのだ。そして、その突き詰めは、小津と組んだ他の作曲家たち、伊藤宜二や斎藤一郎や黛敏郎にはついに出来なかった。小津の意を汲みきれたのは斎藤高順だけだった。だから、このコンビは特別なのである。
はて、小津はどんな映画音楽を求めたのか。私が斎藤高順氏から伺ったときの言葉を使えば、「いつも天気のいい音楽」ということになる。
小津は明治三六年(一九〇三年)生まれだ。サイレント映画を観て育ち、松竹に入り、トーキーになる前に、もう監督だった。
サイレントと言っても映画館には音が溢れていた。弁士や楽士が居た。大映画館には、室内管弦楽団規模のものを常雇いしているところもあった。そして、映画館の楽士と言えば、元軍楽隊員である。《新世界より》を振った田中楽長も、大正のうちに映画館指揮者に転じている。
では、彼らはスクリーンに合わせ、どんな曲をやったのか。興業に力の入った映画では、場面場面でこの曲をと、指定された楽譜が付くこともある。しかし、大方は楽団の自主選曲だ。彼らがよく演奏したのは、マーチやポルカだったようである。要するに、自然とわくわくして身体の動くような曲だ。その音楽は、物語や画面の動きには必ずしも合わない。銀幕上が大愁嘆場でも、楽士は楽しげなポルカをやりっぱなしなんて状態が当たり前である。つまり、場面を説明するための音楽というよりも、所詮は平面上の写し絵に過ぎず、しかも俳優の声も出ず、放っておくと死物のようになりかねないサイレント映画を囃し、生気を吹き込むための音楽なのである。だから、マーチやポルカがいいのだ。
そういう音楽の使い方は、トーキーになると廃れていった。フィルムに音も録音されている。もう弁士も楽士も要らない。画面の役者が喋ってくれるし、効果音も付いている。画面と音が連動し、それだけで映画はかなり活物となる。わざわざマーチやポルカで囃さなくても、生きて動いている感じがする。ならば、トーキーに入る音楽は、場面の説明に徹するべきだろう。怖い場面では、役者の叫び声に不気味な音楽が被る。悲しい場面には泣き声に短調の泣き節が相乗する。そのような演出が当たり前になった。
ところが、小津にはそれが気に食わなかった。彼はサイレントの美意識の中で映画作法を完成させていた。喜怒哀楽は視覚だけで十二分に表現されるのであり、そこに映画芸術の神髄がある。大袈裟な台詞や説明的な音楽で上塗りするのは、下品なのである。音楽は、サイレント時代のように、画面上の喜怒哀楽から超然とし、マーチやポルカで囃しているだけでいい。だから、「いつも天気のいい音楽」なのである。
この思想は周囲に分かられなかった。だが、「最後の軍楽隊員」の斎藤には、元軍楽隊員たちの無声映画館での仕事ぶりを受け継ぐ小津美学が、ピンと来たのだ。だから斎藤は、小津映画のサウンドトラックを、ブンチャブンチャというポルカや、ズンチャチャチャチャ・ズンチャズンチャというマーチのリズムで満たすことができた。それによって、小津のトーキー映画はついに本当に小津らしくなれた。トーキーにサイレントの美意識が召喚されたのである。
斎藤高順を回顧すること。それは、軍楽隊を転轍機として、日本近代洋楽史から世界映画史までを駆け巡る、目眩く体験に他ならない。