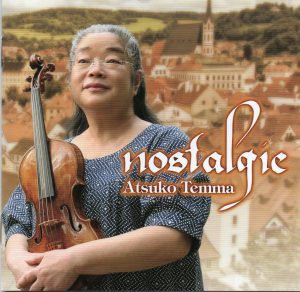「サセレシア」はシャンソンだった?
「サセレシア」は、小津監督にとって特にお気に入りの楽曲でした。最初に使われたのは、『早春』で池部良が病気の同僚増田順司を見舞うシーンに用いられ、続けて増田の葬式のシーンでは小さく流れました。
次作『東京暮色』では、小津監督の強い要望により全編「サセレシア」を使うことになり、タイトルバックから色々なシーンのBGMに「サセレシア」が用いられました。さらに、『彼岸花』でも小津監督の希望によって、中華料理屋のワンシーンに使用されました。
これほどまで、小津監督が「サセレシア」に愛着を示したのには訳がありました。小津監督は、フランスのシャンソン歌手ミスタンゲットが歌う「サ・セ・パリ」や「ヴァレンシア」がとてもお好きでした。昭和20~30年代に流行したシャンソンは、人生の喜びや悲しみ、男女の愛憎や家族愛、時には政治批判なども折り込んだエスプリを感じさせる歌詞が特徴的です。
『東京暮色』は、小津映画の中では最も悲しく重苦しい内容の作品と言われます。山田五十鈴と原節子、有馬稲子による家族の葛藤、愛憎劇を軸に描かれた作品ですが、ここで画面によく合った悲しい音楽を用いると、映画そのものが救い難いほど暗い作品になってしまうことは明白です。そこで小津監督は、人生賛歌のように明るい曲調ですが、人間の内面に潜む愛憎や悲哀を表すようなシャンソン風の音楽を求めたのではないでしょうか。
初めて『東京暮色』を観たとき、悲しいシーンのバックに流れる「サセレシア」のどこか陽気なメロディーに、ある種の違和感を覚えました。映像と音楽が全く逆の印象を与えることにより、観る者の感情を一層増幅させるという、かつて黒澤明監督と早坂文雄氏が採り入れた対位法を思い出しました。もちろん、小津監督はただ辛く悲しいだけの物語を描きたかったわけではありませんでした。
「いくら、画面に悲しい気持ちの登場人物が現れていても、その時、空は青空で陽が燦々と照り輝いていることもあるでしょう。これと同じで、ぼくの映画のための音楽は、何が起ころうといつもお天気のいい音楽であって欲しいのです。」
こう語った小津監督は、シャンソンの歌詞にあるような、どこか楽天的な人生観とエスプリを感じとって欲しかったのかも知れません。あらゆる哀しみを背負って、それでも希望へ向かって歩き出すラストシーンが、そう暗示しているように感じました。
「サ・セ・パリ」と「ヴァレンシア」をモチーフにした「サセレシア」は、8分の6拍子のリズムと独特なメロディーラインを持ち、明るく陽気な曲調でありながら、どこか哀愁と陰影を感じさせます。小津監督の目論見通り、『東京暮色』のストーリーには「サセレシア」が醸し出す、シャンソン風の独特な雰囲気が正解だったのです。世間の低評価にも関わらず、小津監督が『東京暮色』と「サセレシア」に特別な愛着を表す理由と言えるでしょう。